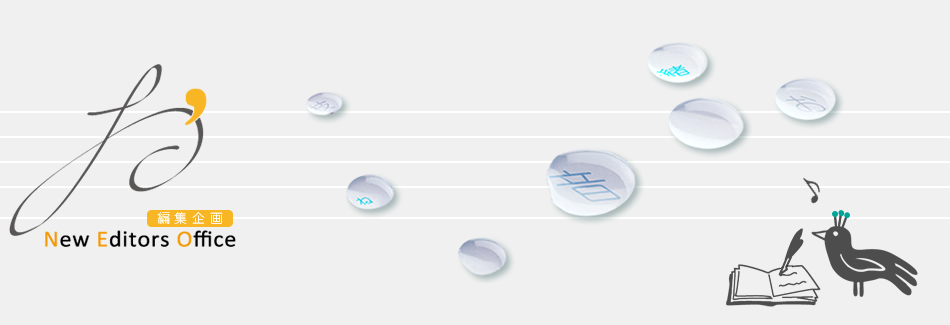清水博先生のお話を聞くたびに、いつも、東本願寺の二枚の看板を思い出していた。2012年3月、当時82歳だった父が心臓弁膜症の手術を受ける日の朝のこと、看板に書かれた言葉に、はっとした。
「バラバラでいっしょ」
別々でも同じ人間、それとも、互いが別々の個を保ちながらひとつに融け合うイメージ。
カタカナとひらがな合計9文字の鮮やかなキャッチコピーである。
初めて卵モデルの黄身と白身のたとえを聞いたとき、すぐに頭に浮かんだのがこの言葉だった。
もうひとつの看板には、こうあった。
「今、いのちがあなたを生きている」
この言葉は、いのちは自分の所有物でなどない、むしろいのちという大きなエネルギーが、あらかじめ存在している、と、言い切るかのようだ。生クリームの口金のように、無数の小さな穴から送り出されたいのちが別々の形につくられ、そこにちょん、とそれぞれの名をつけたものが、それぞれの自分にできあがる。となると、自分は、広大無辺のいのちの表現媒体のひとつにすぎない。
場の研究所の勉強会には、2013年の1月から時々参加し、それまで耳にしたことのない数々の貴重な話を聴いた。とりたてて「場」をテーマとした活動をしていなかった私は、発言する内容をもたず、ただそこにいただけだった。創業から18年かかわった会社で働きすぎ疲れ果て、「心身の健康が維持できない」ことを理由にその1年前に退社していた。
その日は、柳生耕一先生が新陰流について話をされた。『生命知と場の論理』に新陰流の「活人剣(かつにんけん)」のことが書かれていると知っていたが、その時まではまだ難解に感じていた。清水先生は、すっくと立ち上がり、それを実演してくださった。対峙する敵の前に「さあ、お斬りなさい!」と、自分を差し出してみせたのだ。
なんという危険な行為かと思いきや、打ってくる敵に一瞬の隙ができる、そこを自分の中心線(人中路)をまっすぐに斬り落とす。それが百発百中無敵の剣なのだ。なぜそんなことができるのか。それは、相手と自分を切り離さず、場の中で一体としてとらえるためだという。
これもひとつの「バラバラでいっしょ」かもしれない。そして、身を危険にさらして相手を動かすことは、小さな自分ではなく、大きないのちのはたらきを味方につけてこそできるものかもしれない。
場の理論の中で重要なのは、「与贈(よぞう)」という目に見えない行為である。「与贈」とは、名前を隠した贈り物である。作者の名を刻むことのない日本料理や民芸品の静かな美しさの奥には、食べる人や使う人に向けて贈る心が隠れている。沈黙の力が物や行為に宿り、人を惹きつける魅力を発して、世界を確実に豊かにしていく。
映画・「ALWAYS三丁目の夕日」で、少年に万年筆を贈るサンタクロースも名乗らずに立ち去った。どんな人も、クリスマスぐらい誰かに小さな贈り物をしたくなる。それは、誰もが心に贈り物の種をもって生まれているからだと思う。そして、貧しい大人たちは、贈り物をもらった少年と同じくらい幸せな気持ちになった。
誰もが、生まれ、生きていくことによって、この世に贈られた贈り物としての自分に出会っていく。つらく苦しい人生を歩む人も、自分という存在が贈り物であると信じ、自分の中に埋まっている贈り物の種のことを時々考えてみるといい。どんな自分であっても、いつか誰かに小さな贈り物をする日が来る。そして、贈り物をしたとき、自分も思いがけない贈り物を手にしていることに気がつく。それが「与贈循環」ということなのではないかと、ぼんやり考えてみる。
※清水博先生のお話はこちら