場の研究所所長である清水博先生の『近代文明からの転回』(晃洋書房)の冒頭に、真壁仁の「峠」という詩が引用されている。東北大震災という未曽有の災害を経ても、相も変わらず個人の富を守ることに汲々とする現代人に、「今、私たちは峠の時代にいるのではないか」と、穏やかに語りかける先生が、4月14日、学士会館で開かれた「親鸞仏教センターのつどい」で、「自己組織する〈いのち〉――人間の死生観を超えて」という題で話をされた。
この日何より素晴らしかったのは、手入れをせずに放置した自宅のプランターの映像だった。人の細胞が、日々死んでは生まれ変わるように、〈いのち〉の循環の中に、死はごく自然に含まれている。「科学」を盲信する人は死の概念を嫌うが、どこにでもあるプランターの中に、死を含んだ〈いのち〉の共存在を、この日、誰もが目撃した。死は無駄にはされず、土に還って自分以外の植物を生かしている。こんなありふれた情景は、何度も目にしてきたのに、死が生に与えた大きな贈りものに気づかずにいた。
清水先生は、いつも〈いのち〉を括弧つきで使い、「活き」を「はたらき」と読ませる。これは、〈いのち〉を切り刻んで分析的に解釈する「生命」という冷やかな名詞への抵抗である。科学は、ひとつの認識の方法論にすぎない。それでも、〈いのち〉の話を科学の論理で語るところに清水先生の学者としての矜持がある。
走り書きのメモをもとに、できるだけ語り口を再現するべく、以下に講演の再録を試みた。
弱さに目を向ける
地球は温暖化し、大きな変化が起きています。近代文明は、強者の立場から見ると、競争原理で動いている世界です。しかし、地球がこれだけ狭くなってくると、競争原理では紛争を止めることができません。一緒に生きていくためには、弱い者を大切にしなければならないからです。
地球は、〈いのち〉の居場所です。この居場所は、競争原理では守ることができず、共存在原理で守らなければなりません。ここで私が「共生」という言葉を使わないのは、「死」がもっている大きな意味を、「存在」のもつ大きな意味と同じだと考えているからです。
共存在を考えるには、どうすればいいでしょうか。地球が持続していくためには、人間だけでなく、弱い生き物も一緒に生きていける居場所であることが必要です。その方針を誰がどういう論理でつくり出すか考えたときに、政治家にはまかせられません。それでは、科学にその論理をつくることができるかというと、残念ながらそれもできません。
対象を切り離す科学
科学の認識のしかたは、地球を人間との関係を断ち切った対象としてとらえるものです。その場合の地球には、自分たち人間は存在しないため、自分自身を含んだ問題として認識できていないのです。
生命科学とは、ひとつの観念あるいは概念ともいうべきものです。その基礎は物質に帰着しますが、〈いのち〉は、物質ではありませんし、生命科学では地球の問題には間に合いません。それでは、宗教はその問いに答えることができるでしょうか。宗教が、現在地球上で果たしている役割を考えれば、これもあまり期待できないと思います。
居場所にも〈いのち〉がある
〈いのち〉の居場所としての地球がこの先も存在し続けるために、何を考えればよいでしょうか。人間のことだけを考えていてはいけません。人間も人間以外の生き物も含めたさまざまな〈いのち〉の共存在が持続する必要があります。そうすれば、的確な答えを出すことができるはずです。
地球は〈いのち〉の居場所ですが、この居場所にも〈いのち〉があります。だからこそ、そこで生き物が生きていくことができるのです。これは、家庭を考えてみるとよくわかります。家庭は、家族が共存在する居場所であって、単なる住居とは異なるものです。住居であれば売り買いの対象になりますが、家庭は売り買いの対象にはなりません。
〈いのち〉とは、名詞ではなく、そこに存在し続けようという能動的な活き(はたらき)のことです。科学の言葉でいうと、地球は複雑系(注1)です。東北の復興の問題は、居場所の復興の問題と深く関係しています。
私が3年前に上梓した『コペルニクスの鏡』(平凡社)は、大人向けのお話ですが、書店では、児童書に分類されています。興味深いことに、実際には、文学部の先生がピントはずれの感想を口にし、中学1年生の生徒が内容を的確に理解していました。東北大震災を経て、「人間以外の生き物のことも一緒に考えよう」というメッセージをこめて書いた〈いのち〉についてのお話です。
〈いのち〉の居場所の二面構造
〈いのち〉の居場所には二面構造があることを考えなければなりません。自己の外に存在する外在的世界は、客観的に観察できる科学的な世界です。これは明在的な物質の世界です。しかし、〈いのち〉は、外側の世界にはありません。自己の内部にある内在的世界にあるものが〈いのち〉です。
これは、宗教的な表現では、暗在的な「縁」の世界ともいえます。どういった構造になっているかはわからないのですが、外在的世界が内在的世界の影響を強く受けていることはたしかです。その変化のしかたはいまのところよくわかっていません。また、内在的世界と外在的世界は直接的にはつながっていません。
これは、東本願寺の曽我量深のいう「分水嶺」の論理に似ているのではないかと思います。地上に菩薩、天上に阿弥陀如来がおられ、娑婆と浄土は、元はひとつであるという考えです。内在的な世界も、外在的な世界も、どちらか一方だけでなく、両方を合わせて〈いのち〉の居場所なのだと思います。
例えば、ひと組の夫婦の離婚は、外在的な変化ですが、内在的世界の影響を受けたできごとです。どんなふうに影響を受けているかは、日本の総理大臣と中国の指導者がいて、彼らの内在的世界によって両国の関係がつくられるのと同じです。ですから、「内在的世界はない」と考えていることが近代文明の大きな誤りなのです。
粒としての〈いのち〉と場としての〈いのち〉
では、「地球の内在的世界を知っているか」と問われれば、「いや、ちょっとわかりません」と答えなければなりません。
外在的世界では、粒としての〈いのち〉があり、内在的世界には、場としての〈いのち〉があります。それはちょうど役者と舞台の関係と同じです。舞台という居場所の〈いのち〉がなければ、役者は生きていけないのです。
いくら仲のいい友達でも、私の〈いのち〉はくっつくことはなく、西田哲学にいうように、個はひとつひとつちがっていて、同じ粒にはなりません。しかし、内在的世界では、〈いのち〉は、場として見えてきます。仕事に出た時の自分も、家庭に帰ると、家庭という舞台の中で役者としての〈いのち〉を表現して生きることになります。そのように、〈いのち〉の居場所には〈いのち〉のドラマが生まれるのです。
内在的世界では、場を共有していることで、粒としての〈いのち〉が互いにつながることができます。ちょうど量子力学で、素粒子は、場であり、その場から粒が生まれるのと同じです。フェルミ粒子は、絶対にほかの粒子とは同じ状態になりません。だから宇宙はできていくのです。〈いのち〉は、同じ性質ではない多様性をもちながら、一方では場としてひとつにつながった世界なのです。
〈いのち〉の与贈と無名の人
大事なことは、個としての粒の〈いのち〉を、場としての居場所の〈いのち〉にプレゼントすることで、私はこれを〈いのち〉の「与贈(よぞう)」と呼んでいます。与贈は贈与に似た言葉ですが、大きなちがいがあります。それは、贈与が、粒の〈いのち〉を贈り手の名前をつけて与える行為であることです。お金や土地など、「俺がやった」と主張するのが贈与です。
これに対し、与贈という行為は、誰がしたかわかりません。場の〈いのち〉を贈り手の名前を消して与えるのです。私の学生時代にあった奨学金制度では、ホンダ技研の本田宗一郎さんや藤沢武夫さんなどが、自分の名前をかぶせない奨学金を学生に提供してくれていました。これが与贈ということです。
日本文化には、与贈の精神があります。日本料理の土井善晴さんは、「理想の日本料理では、料理人の名前が消える」と言っています。料理そのものがおいしいのであって、つくった人の名前は邪魔なのです。そのあたりが、フランス料理などとちがうところです。
また、柳宗悦(やなぎむねよし)が主張した「民芸美」は、作品に名前をつけようとしない、むしろ名前のない職人の仕事に光を当てたものでした。「無有好醜の願(むうこうしゅのがん)」は、親鸞とも関係があります。私の国には醜いものはないのだということです。美醜や強い弱いという視点でなく、それを超えて本質的な存在としての意味を追究しています。このため、民芸の美しさには人に訴えてくるものがあるのです。
〈いのち〉の自己組織
日本文化は、場の文化であり、その本質には与贈があると思います。なぜ与贈が大切なのかというと、生き物から居場所へ与贈された〈いのち〉が、居場所の〈いのち〉として、自己組織的に統合されるからです(注2)。このことに、私は昨年気がつきました。
『コペルニクスの鏡』を書いた時、2つの自己組織のことと、東北の復興のしかたを考えていました。イベントをいくらやっても、その時の情感が一時的に高まりますが、復興にはつながりません。それは、イベントが外在的な世界へのはたらきかけに終わってしまうからです。『コペルニクスの鏡』を書いた時には、それがまだわかっていませんでしたが、あとになって、内在的な自己組織ができなければならないのだ、と気づきました。
内在的世界で自己組織された居場所の〈いのち〉が、「愛」や「大悲」として生き物の〈いのち〉を生む。ここに救いが生まれます。被災地の復興だけでなく、家庭生活においても、ポイントとなる本質は〈いのち〉の与贈です。自分の家庭に何も与贈しなければ、家庭生活は崩壊してしまいます。会社もまた同じことでしょう。
〈いのち〉は居場所から返ってくる
生き物が居場所に与贈した自己の〈いのち〉は、生き物につながったまま、居場所で自己組織され、大きい〈いのち〉になります。この自己組織された居場所の〈いのち〉が、神や仏の霊として、生き物の内部に返ってくるという言い方もできるかもしれません。
キリスト教では、パウロがローマの信徒に宛てた手紙が8通あります。日本の縄文時代のことです。パウロという人は、ローマの市民で、はじめイエスを迫害していました。それが、復活を体験し、大きく転換しました。この人は、ギリシャ語の読み書きができ、生涯に3回旅をして、キリスト教を広めました。
パウロは、〈いのち〉が肉の支配下ではなく霊の支配下にあることを知りました。これがわかると、〈いのち〉の活き方が変わります。しかも、内在的世界への〈いのち〉の与贈とその結果は、生と死を分断しません。
生の時は、個を離れた居場所から、循環する〈いのち〉を生成します。死の時は、個を離れて居場所に縁として戻り、居場所の〈いのち〉の自己組織の拘束条件となるのです。どのような自己組織をするかは、「縁」が決めることです。
いろんな人ができるだけ居場所に対して与贈して、全体の〈いのち〉が自己組織されていく。自分の〈いのち〉は、場の〈いのち〉につながっているので、〈いのち〉をプレゼントしたことによって、粒としての個人も、自分の〈いのち〉が富んでゆくのを感じます。ですから、仏を信じたことによって、〈いのち〉の質が変わらなければ、それは信じたことにはならないのです。
(つづく)
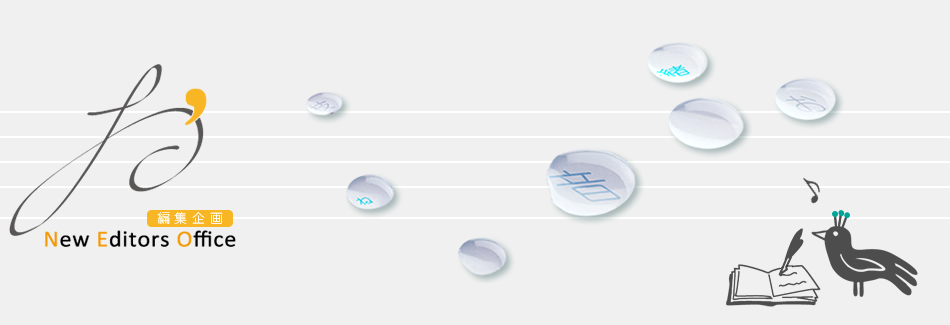
「峠の時代の〈いのち〉と富の話(1) 清水博氏講演・「親鸞仏教センターのつどい」にて」への1件の返信
現在コメントは受け付けていません。