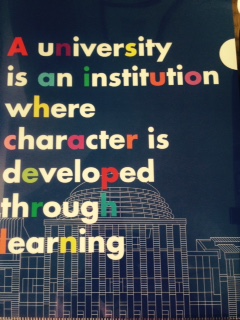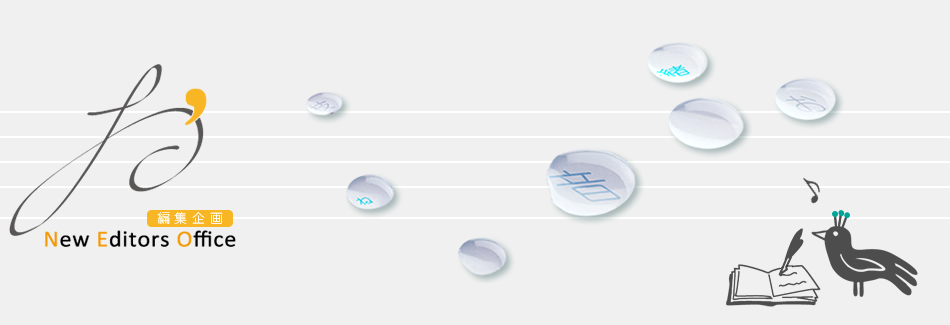松田雪絵氏(埼玉県立伊奈学園総合高等学校)の報告
1.多文化言語共存社会で生きる人材を育てる
伊奈学園総合高等学校というユニークな言語教育に取り組む学校があることを初めて知った。同校は、1984年に併設型の中高一貫校として創設され、普通科でありながら「学系」という独自の分類による人文、理数、語学、生活科学、スポーツ科学、芸術、情報経営の7科を設け、興味や適性に合わせて時間割を組むことができる。
個々の興味に応じた科目強化が可能で、語学系でフランス語を選択して服飾を学び、アフリカのマリ共和国で職を得た生徒や、人文系で美大をフランス語で受験した生徒などもいる。これは、語学系で3年間フランス語を学べばフランス語で大学受験ができると同時に、別な科の生徒でも同レベルを習得できるという同校のシステムによる。
松田氏は本来英語教員資格をもち、2名のフランス語教員のうちの1人である。他に非常勤教師が1名、フランス人の外国人指導助手(ALT)1名、スイス人非常勤講師1名がフランス語教育の陣容である。フランス語履修者は1年次106名、2年次67名、3年次42名と過去最大人数に増えている。松田氏はエネルギーに溢れ、短時間に大量の内容を伝えるようよく準備された発表に圧倒された。
この学校は外国語を種類によって区別せず、英語でもフランス語でも高度なレベルまで学ぶことができる。学習のしかたは生徒個人の意欲と決断に委ねられるため、第1外国語、第2外国語の別もない。反面、受験希望言語が異なる生徒が同じクラスに混在することは、教師の指導を難しくする。それでも受験だけにとどまらない多様なニーズに配慮した教育方針から、教師の注ぐエネルギーは相当なものである。
「外国語教育でどんな人を育てるか」という教育目標の到達点は、きわめて明確である。「多文化言語共存社会の中で望ましい人間関係を構築できる人」を育成を目指す。
この要件として
・自律した学習ができる――生涯学習
・コミュニケーション能力
・異文化間能力
・思考力、論述力、批判的精神
を上げる。
これにより、高校入学時は受け身で自分で考えることもせず、楽しくなければすぐあきらめるような生徒を、大学や社会で必要とされる能力をもった若者へと変身させるのである。
入学時の生徒には、外国語とは英語であり、外国とはアメリカという画一的なイメージしかない。また、ケータイ世代ゆえ世代間コミュニケーションの経験もなく他者への配慮にも欠ける。これを踏まえて、教師は、理念の一方的な押しつけにならないよう小さなステップを丁寧に積み上げて、高校3年間で大学に橋渡しする役を引き受けている。
2.ノートを通して丁寧に教師がフォロー
ここではノートが最大限に活用されている。まず、驚くほど多いスペルミスには、ノートに「チッチッチッ!」と注意する猿のハンコを押して戻し、「私のノート、こんなにチッチッチッ・モンキーがいる!」と気づかせることから始める。丸暗記やフィーリングで覚えないよう、スペルと発音の関連など法則性と理屈を教え、テストで間違った箇所を復習するテスト直しノートを作らせる。
生徒たちの学習のしかたは、1日目にA、2日目にB、3日目にCだが、教師は、「人間は忘れる生き物である」という真理を厳かに伝えたのち、1日目A、2日目にAB、3日目ABC、4日目から6日目までABCをやらせる。文句を言いつつも、生徒たちは素直に従う。
この成果は抜群で、次のテストでは17点が79点、30点が80点になるなど、少なくとも20点以上の改善がみられる。さらに、この学習を経験した生徒が、ほかの生徒を巻き込んでいき、自然と自律型になっていくというメリットもある。
部活優先の生徒たちにコンクールへの参加も義務づけている。暗誦と、スケッチとよばれる寸劇を行わせ、ここで生徒は、「観客を相手に言葉を発し、伝えるとはどういうことか」を学習せざるをえない状況に初めて遭遇する。彼らの苦手な他者への気遣いや想像力がいやでも刺激され、育っていくみごとな場の設定である。このような場は、大人にも必要かもしれない。
面白いのは、テストの点が悪くても発音のいい子が上手に暗誦ができたり、演技力のある子がプレゼンテーションにすぐれている点である。これが若い生徒たちに大いなる自信を与え、その自信が彼らの自己教育をさらに促進する原動力となる。
教育に配慮されているのは、
〇中・長期的に物事を進める力
〇自分の能力を最大限に発揮する経験(松田氏は「とことん」という言葉を口にした)
〇テストのための勉強から高度な次元の学びへ
〇学び高め合える学習集団作り
である。
教育者として、松田氏は言う。
「今の日本にはすぐに役に立つものだけを学びたがる傾向がありますが、この年頃ならまだそれを直すことができます。『わからない』という認識は大切です。発表のために調べていると、知らないことにぶつかる。さらに調べるともっと知らないことにぶつかって、どんどんハマっていきます。この姿勢が彼らの『知りたい』という姿勢につながります。大学で学んだことが社会で役に立たないなどとは言わせたくないのです」。
集団づくりもまた重視される。「この子たちの前なら、わからない、とか、まちがったことも言えるという仲間。上の学年など縦のつながりも意識しています」(松田氏)。フランス語を、教科ではなく「言葉」として認識して、使う場面を考えさせることが大切にされている。
言葉が発せられる以上、必ず何らかの場面や状況がある。誰が誰に向かって話すのかを考えなければならない。自分と同質の相手としかコミュニケーションをせず、相手に配慮する発想のない中学生が、学習を通して自然と目を開かれていく。
松田氏は、使える人と機会は逃さない。授業見学に訪れた来日間もない大使館のフランス人に、「旅行会社ごっこ」よろしく日本各地の場所の説明をさせ、どの企画がアピールするかを生徒に競わせたりもする。
「英語も満足にできないのに、ほかの外国語を勉強してどうするの?」という凡庸な質問には、「別の外国語を学ぶからこそ、複眼的な目が育つ。外国語は英語だけではない。いろんな文化があることを知って、自文化を相対的に見ることを学ぶ。『わからない』と気づくことはとても大切です」と述べる。
3.教員の資質をどう向上させるか
フランス語の学習が言葉に対する生徒たちの意識を変えていくことも、アンケートの結果で示された。多様な文化への理解が進むにつれ、学習の姿勢は前向きになり、もっとできるようになりたいと欲も出る。3年生に進む頃には、世界や日本の見方を自分なりに見つけている。教師の情熱なくしてできることではない。
問題にされるのは、よい教師をどう育てるかということである。それぞれに組織や環境による制約もあることは十分想像できるが、教師の勉強も一生物である。
松田氏は、「ひとつの組織内で停滞せず、外へ出ていろんな人の話を聴くと教師自身の成長につながる。外国語を教える教員に、別の言語の習得を義務づけてもいいのではないか」と、かつて「デモシカ」と呼ばれた時代もある「教師」のプロ化を望む。
百合氏は、雑誌「英語教育」にかかわりの深い教員たちの勉強会をはじめ、教員が教授法を学ぶ場をいくつか挙げ、知識以外の実地の困難を踏まえて、教員の成長の必要性と教員の指導者の重要性を指摘した。
獨協大学外国語研究所主任研究員の岡田圭子氏が最後に、「教員養成には危機感をもっています。スイスを訪ねた時に優秀な学生がガイドについてくれましたが、仏語圏の彼女が英語教師の資格をとるには、アメリカに留学してマスターをとって、さらにまた留学をして勉強をしなければ資格が得られないという厳しさです。科目間協力なども日本ではまだまだ考えていかなければなりません。母語を含め、広い意味での言葉をどう育んでいくかを考え続けたい」と締めくくった。
教育者が常に能力を向上させ、教育内容の改善に挑戦していることを知り、希望のもてるシンポジウムだった。配布資料に含められた大学のクリアホルダーに、「A university is an institution where character is developed through learning」という初代学長で哲学者の天野貞祐氏による獨協大学建学の精神がカラフルに印刷されていた。