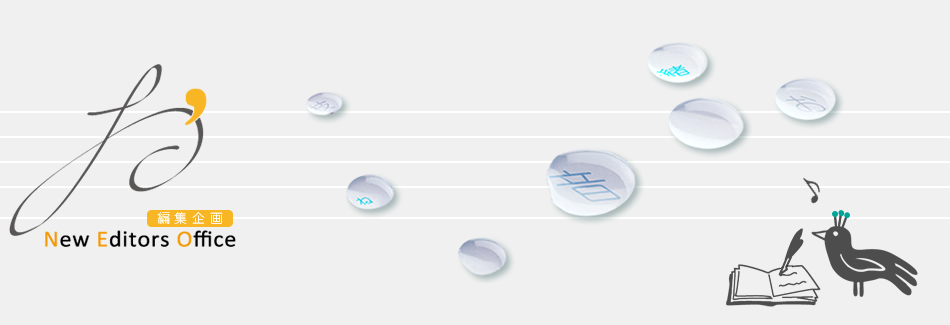最近、医療や看護の本に「スピリチュアルケア」という言葉を見かけることが増えた。治す医療とケアの看護が補い合うのは当然として、人間を単に部分の集合ととらえていては済まない状況が増えているためだろうか。たとえば、がんの末期を宣告された人、耐えがたい喪失体験、大切な人の重い病気や障害に苦しむ人には、処方する薬がない。宗教的なものや医療以外の救いを求めるのは、ごく自然なことである。
スピリチュアリティの定義が知りたくて、9月6日、上智大学の日本スピリチュアルケア学会学術集会で2つの講演を聴いた。川中仁副学長の基調講演「カトリックのスピリチュアルケア」と、作家の柳田邦夫氏による記念講演「人生の総括とスピリチュアリティ」である。自分なりに理解したかぎりでは、スピリチュアリティとは、小さな自己にとらわれずに、自己を超えた大きな存在や他者の存在に目を向ける真摯な心の態度をいうのではないかと思った。それは単に頭の上に飾るものではなく、より深く腹で感じるたしかな自分のよりどころのように思われた。
人生の総括とスピリチュアリティ(柳田邦夫)
ノンフィクション作家として有名な柳田氏の話は、傾聴と物語の力についてであった。
「スピリチュアル・ペインをもつ人に聞き書きをして記録するということに出会い、ケアの領域にこんなものがあるのかと思いました。本は一冊一冊表紙があり、デザインがあり、タイトルがあるように、聞き書きが、人間ひとりひとりの人生を考えることになるのです」
柳田氏は、スピリチュアリティを、まず存在の意義と定義した。「この世に生まれ育ち、社会生活を経験し、やがて死ぬことの意味の全体がスピリチュアリティではないかと思います」。このあと氏の語りの中で、幾通りもの表現でスピリチュアリティが語られる。
心理学者の故・河合隼雄氏に、『物語を生きる』という著作があるように、人の人生は、長編小説に似ていくつもの章に分かれる。物語ることによって、それまで無意味だと思っていたつらい出来事に深い意味があることに気づく。最終章を大きな文脈としてどう書くかという問題があり、科学とはちがう「物語の一般性」がある。
●「サクリファイス」とマタイ受難曲
科学の特徴は、普遍性であり、因果関係をもった実証性であり、再現性である。これに対し、物語は、個別性と多様性をもち、一過性の瞬間の真実がある。「意味のある偶然」とも称されるこの瞬間の真実には重い意味があり、その時に起こった不思議なことが、クライアントの力になることがある。
柳田氏にもそんな経験がある。25歳の次男が自ら死を選んだ。遺体を引き取って家に連れ帰り、居間に安置していたときのこと、長男が何気なくリモコンでテレビをつけた。タルコフスキーの映画「サクリファイス」が終わりかけ、マタイ受難曲が流れていた。それは次男が好きな曲だった。彼は無宗教であったが、この不思議な偶然は、大きなものが見守ってくれているという残された者へのメッセージに思われ、大いなるなぐさめとなった。こんなできごとがどれほど人を力づけ、生き直す勇気をくれることか。これが物語のもつ意味である。
●見習い看護師と傾聴
河野博臣の『死の臨床』に、1970年代に神戸で出会った初老のがん患者と見習い看護師の話がある。高齢の婦人は、重い胃がんにかかっており、苦しく、医者にも看護師にも口をきこうとしない。見習いの看護師は、なすすべもなく、棒立ちになり、かける言葉もない。そのうち、無意識に婦人の背中をさすり、腰をさすった。すると、夫人は、背を向けたまま、「ありがとう。少し楽になった」と言った。それから、その見習い看護師にだけ、自然に会話するようになった。そして、自らの人生を語り始めた。その中には過去の喜びもあった。若い見習い看護師は、ただ聴いていた。
「そうですか」「よかったですね」
それが、はからずもロジャースのいう傾聴になっていた。婦人は、がんの腫瘍を赤ちゃんのように感じ始め、苦しみは少なくなり、静かに旅立った。
スピリチュアリティなどという言葉を誰も知らない頃の話である。人間は、自分の人生を誰かに知ってほしい。真摯に耳を傾けてくれけると、それが大いなるなぐさめになり、癒しになる。自分の人生や存在がかけがえのないものであると感じることが、不安や恐怖をやわらげる。
●聞き書きボランティア
宮崎のホスピスに、「宮崎聞き書き隊」というボランティア組織があり、聞き書きボランティアの育成も行っている。聞き書き選集の『話しておきたい、私のこと』にあったある男性の満州での壮絶な体験にいたく感動した。日本へ引き上げてきてから、自身の過去について口を閉ざし、黙々と働いてきたその人は、話すことによって、自分の人生を再確認し、家族からも尊敬されるようになった。
物語ることによって、人生の最終章を自分で書くと認識できたら、それが真の人生の始まりとなる。身近な人たちがそれを読んで、共有できることで、絆も深まる。
「自分なりによくやっ」たと、人生をまるごと受容することこそ、スピリチュアリティそのものではないか。
●大きな存在に見られている
緩和ケアには、「生活臨床」という視点が導入されている。
「その星や雲、季節の移り変わり、行事、食べ物、家族……こそが、いのちや死をしっかりと見ている」(徳永進)という感覚は、たとえば、大きな木に手を触れ、木を見るとき、同時に木に見られているという感覚である。
スピリチュアリティは、深遠な宗教的空間だけにあるのではなく、身近な自然の中にある。
子どもは、自然の向こうにある創り手の存在を、理屈ではなく「ある」と知っている。それは、生と死が続いていることでもある。
●「根こそぎ喪失体験」をした小林麻里さん
心の病で青春を過ごし、ようやく39歳で伴侶を得て福島に移り住み、結婚2年半で永訣した。そして原発事故。天を恨んで運命を呪った彼女は、ふと、「ああ、私の魂はこういう人並みの経験がしたかったんだ」と気づいた。若い日、人並みの人生が送れず精神病院に入った自分も、苦しみや悲しみを経験するために普通の世界に戻ってきた、とわかり、『福島、飯館、それでも世界は美しい』を書いた。『それでも人生にイエスと言う』を著したフランクルの思想そのものである。
人は、他者とのコミュニケーションを切断すれば、生きることが困難になる。心の苦悩や不安、葛藤を文章に表現するためには、自己を見つめる作業が必要となる。文脈をつくることは、心の整理にもなる。
生きている自分の確認、生きる方向への心の動き、これもスピリチュアリティである。
●死後生
発達心理学者のエリクソンのライフサイクル曲線は、若い頃を頂点とした放物線が高齢に向けて下降するが、むしろ老いることで成熟に向けて、曲線は右上がりになり、さらに死後生に続くと思う。人の生は、死では終わらない。残された人の心の中で、その人の人生を膨らませ、より豊かにする。
死後生とは、肉体がなくなっても、生きる証(精神性、心)を大切に思ってくれた人の心の中で生き続ける生である。哲学者のジャンケレヴィッチは、「死は生を無にするが、死は逆に自らを無にすることによって、生を意味づけするものだ」と言う。死があるからこそ、その本人の生きる意味、残された人の生の意味もある。
***
途中、柳田氏は、ユーモアの大切さに触れ、淀川キリスト教病院の柏木哲夫氏からひとつ引用して、四隅を斜めに切られた青い真四角の図を映し出した。
「これは、澄み切った(隅切った)青空です」