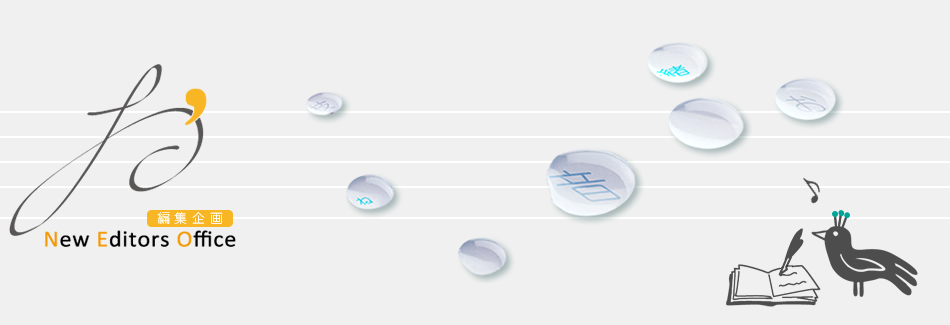ある看護書に、「ケアが侵襲(ストレス)にならないようにかかわる」という記述があった。
善意で行う医療処置も、いいことばかりではない。抗がん剤などの強力な作用をもつ薬は、ある症状に対処するために薬Aを投じると、
その副作用を防ぐために今度はBを投じ、さらにその行き過ぎを正すためにCを、といった具合に、
薬が薬を呼ぶようなところがある。治療が患者を激しく消耗させるひとつの例である。
病院では、必要があって行わなければならない処置もある。手足を縛る「抑制」は、手術後に麻酔から覚めるとき、
者が錯乱して生命維持に必要なチューブの類を自分で抜かないために重要である。
ただし、認知症の患者の徘徊を防ぐためにベッドから離れられないように縛りつけることは、また別の話だ。
呼吸や栄養を助けられて生を継続する患者を、医療者が管理しやすいよう薬で過度の鎮静状態にする場合も、一種の抑制といえる。
このような「生命維持」は、誰のためのものだろう。
以前は、栄養に関する教科書的な知識として、患者の身体的なアセスメントを行い、適切な栄養療法を選択し、
それに合った栄養剤の形状を選んで投与することに何の疑問も抱かなかった。
栄養の専門家が、医師やナースと協力して治療にあたるNST(nutrition support team:栄養サポートチーム)も、
薬より栄養の力に注目されるようになったのだと思っていた。
しかし具体的に考えると、その栄養の投与は、患者の状態を安定させるための「成分の注入とバランス管理」であり、
通常の食事によらずに人を生かすことが目的とわかった。
口から食べられなければ、静脈や鼻に通したチューブから栄養剤を注入することになる。
内視鏡手術で胃に穴を開け、通した管から注入する「胃ろう」も、ポピュラーになってきた。
栄養療法は、「経管栄養」といって、可能な限り消化管を用いた栄養摂取が推奨されているから、
食道を経て胃へと栄養剤を送る経鼻栄養法は、人体にとって悪いことではない。
しかし、当然患者の違和感と不快感は大きい。これを「胃ろう」に変えると、経鼻栄養に比べて患者の負担感が減り、
QOL(生活の質)が改善されるとして一部の人は肯定的だが、感染のリスクがあり、QOL・延命効果ともに疑問視する声も多い。
治療も手術も、死に方も、結局のところ、ある程度は選択の問題になる。しかしその選択を行うには、
あらかじめ自分の考えを整理して、起こりうる事態に備える意思が必要だ。急に運ばれた時、あるいは状態が長引いた時、
自分や家族が何をされるか、きちんと知らなければ、選択などできない。
具体的にわかっている人だけが、中村仁一氏のように、自分の意思と責任で「救急車を呼んでくれるな」
と書き記しておくことができる。
中村仁一氏は、著書『大往生したけりゃ医療とかかわるな』の副題を、「『自然死』のすすめ」としている。
このほか「平穏死」という言葉もよく耳にするようになった。
これは明らかに、病院で受ける延命措置を選択しないことを意味している。女優の賀原夏子さんは、
「生まれてきたように死んでいきたい」と言ったそうだ。
昔は多かった「老衰」による自然な形の死は、自分の意思をよほどはっきり持っておかなければ叶わない時代になっている。
『大往生』は、昔、永六輔氏が書いたベストセラーのタイトルで、ごく普通の人の老いや死についての言葉が紹介されている。
そこにスパゲティという医療隠語が出てくる。何本ものチューブにつながれ、意味もなくそこに生かされているという意味である。
栄養の管、人工呼吸器の管、排泄を管理する管、心臓を管理する管など、最低4種類の管がからだに入った状態だそうだ。
そんな自分の姿を最後の記憶として家族に残してもいいかどうかは、財産のことよりもっときちんと考えるべきことである。
たとえば、死に際の脱水は、意識が低下し、苦痛をなくしてくれる最善の麻酔薬であるという。むやみに水分を与えると、
ぶよぶよと重いばかりの死体ができあがるのだそうだ。
自分のもてる栄養や水を十分に使い切って、きれいに枯れる――そんな死に方もあるのだ。
死にも、健康な死と病的な死とがある。できることなら、よぶんな処置なしに健やかな死を迎えたいものだ。
映画「眠れる美女」では、17年間昏睡状態にあったエルアーナという女性をめぐって、延命を打ち切るべきという人たちと、
彼女が目覚めるよう祈りを捧げる人たちが対立した。結果的に、エルアーナは亡くなり、この問題には一応の決着がつく
自らの心を曲げられない議員ベッファルディが安堵した一方で、目覚めを祈り続けた女優(娘が植物状態の)の表情は、
あまりはっきりとは映されなかった。
もしも彼女のように、年若いわが子が、不慮の事故で植物状態になったとき、延命をしないという決断を、
ある日突然下せるだろうか。植物状態の患者が回復するケースはたしかにある。家族なら、どんな状態でも
生きていてほしいと願うことも多いだろう。しかし、そのようにして生かされている当人は不幸かもしれない。
生かしても、死なせても、家族は罪悪感から逃れることはできない。
だとしたら、エルアーナのように、自然に訪れてくれた死は、ひとつの救いであるだろうか。
大切なことは、医療について、医療だけで考えないことである。哲学や宗教、法律など、人間の幸福を考える
あらゆる分野の知恵を集めて、十分に議論する必要がある。技術を尽くして、人の体を生かしたり殺したりできたにせよ、
それが誰にとっての最善であり幸せであるか。意識を失った本人が何も語らなくな
ったなら、
周囲の人たちは、死について深く考える機会にはからずも恵まれたのだ。
死は、誰かひとりの個人に属するものではない。誰が何を選択してもしなくても、死は、大きなマントのように、
かかわる人々を包み込んで同じ場の共有を強いる。「生活の質(Quality of Life:QOL)」と言う言葉を、
「人生の本質」と読めば、最期のときをどう終えるかは、QOLに深くかかわる問題である。
完璧な準備でなくても、自分や家族の死という場ができるだけ穏やかなものであるよう、時々は死を身近に考える時間をもつようにしようと思う。
(参考文献)
1)中村仁一:大往生したけりゃ医療とかかわるな――「自然死」のすすめ.幻冬舎,2012.
2)永六輔:大往生,岩波書店,1994.
3)長尾和宏:平穏死 10の条件――胃ろう,抗がん剤,延命治療いつやめますか?ブックマン社,2012.
4)日本老年医学会:「高 齢 者 の 終 末 期 の 医 療 お よ び ケ ア 」 に 関 す る 日本 老 年 医 学 会 の 「立 場 表 明 」(2001)
http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/proposal/pdf/old_v_jgs-tachiba2001.pdf
5)日本老年医学会:「高齢者の終末期の医療およびケア」に関する日本老年医学会の「立場表明」2012
http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/tachiba/jgs-tachiba2012.pdf
※日本老年医学会の「『高齢者の終末期の医療およびケア』に関する日本老年医学会の立場表明」は2001年時のもの、2012年時のもの、いずれも気合がこもって一読の価値があります。