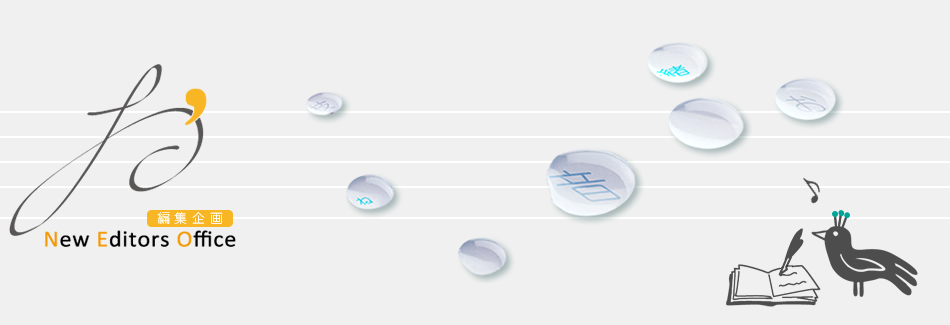◆認知症の「予防」とは何か
2013年9月27日から3日間新潟の朱鷺メッセで開催された第3回日本認知症予防学会。最終日の午後開かれた市民公開講座では、日本医科大学武蔵小杉病院の北村伸氏、鳥取大学の浦上克也氏が登壇し、認知症の最新の情報と地域での活動について講演を行った。
「痴呆」にやや侮蔑的な響きがあるとして「認知症」という言葉に変わったのは2004年12月。要因となる脳の障害の解明も進み、予防を促進することが方針となった。
「予防」という言葉には「手洗い、うがいの風邪予防」のイメージがある。このような「かからないための手立て」は「一次予防」とよばれる。これに加え早期発見・早期治療を意味する「二次予防」と、発症後にも適切な治療により重症化を極力おさえる「三次予防」があり、ここまでを含めたものを「予防」という。「かかってしまうと予防できない」のではなく、段階や状況に合わせ現実的に対策を講じて生活の質を維持していこうという姿勢である。
2013年6月現在で日本の認知症患者は462万人。85歳以上の45%がかかり、65歳以上の4分の1は予備群という。予備群は400万人と推定されているが、「900万~1400万人ではないか」(浦上氏)という考えに立てば、できる限りこれを予防するのは当然である。仮に認知症になっても住み慣れた地域で暮らすことができるためには、周囲の理解とサポートが欠かせない。そのために認知症についてできるだけ具体的に知ってもらうのが今回のような講座の目的となる。
◆早期発見につながる物忘れレベルのチェック
二番目に登壇した浦上氏は、聴衆にビデオを見せてちょっとしたテストを行った。息子に付き添われてクリニックを訪れた母親を芝居上手な模擬患者が演じる。一見どこといっておかしな様子はなくしっかりしているが、話してみると昨夜の食事の内容や交通手段など、息子と答えが大きく食い違う。本人は堂々と年相応の物忘れとしているが、このように自覚がなく気づかれにくいところに認知症のむずかしさがある。
誰でもある年齢になると、若いころほどの記憶力は保てない。記憶力や判断力が低下するのは、脳の神経細胞が減ったり信号伝達が悪くなるためだ。しかしそれらに加えて、これまでできていたことができなくなったり、「見当識」といって自分のいる場所や日時がわからない、言葉の意味がわからないなどの症状があると、その記憶障害は認知症の中核症状と考えられる。認知症の原因は、大きく遺伝、加齢、生活習慣があるとされるが、もちろん単なる老化現象ではなく、「物忘れのために日常・社会生活に支障をきたす状態」をいう。
物忘れが年齢的なものか病気なのかの判断はつきにくい。かかりつけ医に相談して、血液検査やCT画像、血流の滞りを画像で確認できるSPECTなどで調べると、それが年齢相応の物忘れかどうかの診断がつく。ほかに、タッチパネルを使って簡単にチェックできるシステムも開発されて、町内の行事の時に試せるような動きが各地で広がっていることには希望が持てる。
脳血管障害の既往による神経細胞のダメージから起きる認知症は「脳血管型」とよばれ、二番目に多い。このほか、体が傾いて転倒しやすい「レビー小体型」、物忘れは目立たないが同じ行動を繰り返したり、言葉の意味がわからなくなったり言葉が出にくくなる「ピック病」など、脳の障害部分により数種類の認知症の型がある。中でも認知症の半数以上を占め最も多い「アルツハイマー型」では、自分のおかしな言動のつじつまを合わせ、とりつくろうなどの傾向があり、周囲にわかりづらい面がある。それぞれのタイプが単独で出ることもあれば、脳血管障害の既往にアルツハイマーが複合的に生じることもある。
◆アルツハイマーに有効な4種類の薬物
中核症状以外に問題になるのが、アルツハイマー型の一部にみられる奇異な行動や精神症状(behavioral and psychological symptoms of dementia:BPSD)で、周辺症状とよばれる。幻覚や妄想はこれに含まれる。ほかに徘徊や暴言暴力、不潔行為など、介護にあたる人を悩ませるものは多い。何らかの身体的不具合や薬剤の副作用があったり、周囲の環境や対応のしかたなどに原因があることもあるため、環境をよくするよう努め、必要に応じて有効な薬物治療を試すことがすすめられる。
アルツハイマー病では、脳内の神経伝達物質であるアセチルコリンを分泌する神経細胞にダメージが生じ、アセチルコリンが減少する。この減少を食い止めるべく、アセチルコリンの分解酵素であるコリンエステラーゼの働きを阻害する薬物が用いられる。これによって周辺症状に改善がみられるとともに、日常生活上の支障も減らす効果がある。ポピュラーな薬としては、アリセプト、レミニール、リバスタッチの3種が知られ、重症度によって使い分け、量も調整する。この3種がコリンエステラーゼ阻害薬であるのに対し、新しくNMDA受容体阻害薬としてメマリーという薬も登場している。NMDA受容体とはグルタミン酸の受容体で、これが過度に活性化した場合に脳内の神経細胞が障害されることから、この働きを抑えることで症状進行を遅らせるものである。
服薬については、まちがいなく本人がそれをのんでいるかの確認も含め、医師以外の医療スタッフや福祉の専門職種が連携して見守る姿勢も重要となる。28日のランチョンセミナーでは、大阪大学の数井裕光氏により、ケアにかかわるすべての人が一冊のノートを介して情報共有することで互いに理解と信頼を深め、家族の安心とケアの質の向上をもたらした実践例も報告された。
◆薬以外に環境をよくして症状改善も
治療中に食欲が落ちた認知症の男性の話は、いかにもありそうなエピソードだった。家族はてっきり薬の副作用と思っていたが、本人によくよく聞いてみると「宅配のお弁当がおいしくない」という。それが証拠に大好きなフランス料理に家族が連れて行くと、喜んでたくさん食べた。この例にも通じるが、従来、認知症にかかると、本人には何もわからないと考えて周囲が先回りして何もかも決めてしまう本人不在の対処がなされることが多かった。しかし、認知症は何もかもわからなくなる病気ではない。まず本人の気持ちに注目し、本人本位で接することの重要さがさりげなく指摘され、薬だけで治療が成立しないことも強調された。
本人に異常な行動や精神症状がみられる時は、ストレスの多い時でもある。これも、工夫して本人にとって環境をできるだけよいものにすることで薬を用いなくとも状態を改善させる効果があるという。もちろん家族にもストレスが高く、十分にケアできないという事情もあり、介護者は「第二の患者」でもある。日本医科大学武蔵小杉病院では、大学が中心となって「街ぐるみ認知症相談センター」を据え、あらゆる相談に応じ、行政、医療、福祉、市民のネットワークづくりを支援している。地域全体で予防に向かうことは種々の負担の軽減につながるため、市民や専門家向けの啓発にも力を入れている。
この講座とは別にみたポスターの発表で、デイケアになかなか参加しない男性を集めるためにギャンブルゲームのプログラムを組んでいる介護施設があった。楽しみながら前頭葉を活性化、脳を若返らせるいい方法だと思った。医療につながらない予備群の認知症予防に地域ぐるみで行うために、石川県のNPO法人日本認知症予防研究所のように、認知症予防のための人材として「脳活コーチ」の育成に取り組んでいる例もある。困っている人を助け、健康な人の意識も高める種々の活動が全国に広がることで、認知症にかかっても住みやすいまちがたくさんできるにちがいない。