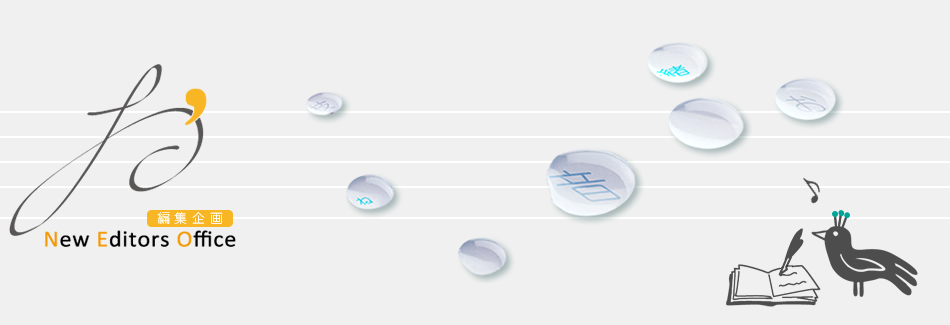ヒトと世界と病気
7月初め、尼崎で久しぶりに横田直美先生にお目にかかり、最近のご活動など伺った。
昔から、人間をホリスティックに捉える視点は変わらない。漢方をはじめ、ホリスティックな医療について、あちこちで講義する機会も増え、2~3年前からは、その対象を小学生にまで広げている。
語り出しの言葉は、彼らにとっておそらく新しい視点の提案である。
――私たちは、今、この世界のどこにいるの? それを判断するために、自分たちの行動が世界にどんなふうに影響を与えているのかを一緒に考えてみよう。
こんなふうに問いかけられた子どもたちは、さぞかしびっくりしたことだろう。
風邪をひいたりお腹が痛くなってかかるお医者さんは、あまりこんなことは言わない。
症状に対して出す薬はメニューのように決まっていて、自分たちはそれをもらって帰り、きまりに従って食前や食後に飲むうちに症状は治って、「病気をお医者さんに治してもらった」と思うのがふつうだ。
ありふれた病気をして、それが自分とどう関係したかなんて、冷たいものを食べすぎたからかな、くらいは思っても、深くは考えないし、ましてや、そこに世界のことを結びつけたりはしない。しかし、現実には、だんだん大人になるにつれ、世界と自分の関係を考えさせられるような病気や障害が少なくないことに気づき始める。
医療に必要なカウンセリングマインド
昨今の病気は、抗菌剤をまじめに服用すれば治るといったわかりやすいものとは異なってきている。中には、検査をしても数値に異常がなく、見てわかるような手がかりが得られにくいものもある。
いわゆる不定愁訴に悩む女性は、従来型の西洋医学では心療内科、精神科、更年期外来など、複数の科を受診するしか手立てがない。すると、別々に処方された薬を同時に飲むポリファーマシー(多剤併用)に陥り、必然的に薬の量が増える。大量の薬を飲むことが、症状改善よりむしろ悪化につながることは、よく指摘される事実である。
医師にもいろいろな人がいる。詳しい説明もせずに「1日40錠」と申し渡して、理由を尋ねても「飲まなければならないからです」としか答えてもらえなかったりする。精神科系の薬であれば、オーバードーズ(過量服薬)になり、医療が薬への過度の依存に手を貸すという深刻な状況を生むことも多い。
悩める患者と不確かな症状に対し、医師は、どうあるべきなのだろう。
横田先生の答えは、シンプルだ。
「医師がカウンセリングマインドをもつこと。患者がうまく言葉にできなくても、医師や看護師にそれを上手に引き出す力があれば、医療の内容は格段にグレードアップします」
一部では応対の丁寧な医師も増えているが、尋問のように根掘り葉掘り問いただして、患者がつらくなるような情報の取り方をする人もいる。聴く力は、医師と患者の良好な信頼関係に必須の条件である。
どこで働く医師であっても、そうした勉強はできるはずだ。ヒトの心への対処のしかたを心得、ドクターハラスメントなど絶対にしない医師が増えてほしいと、すべての患者は願っている。
西洋薬と漢方薬
はっきりしていることは、「治る」という現象の前で、医師の指示や薬品の力には、限界があるということだ。
不定愁訴のように分断した科で別々の診断を受け、たくさんの病名がつくことを、横田先生は「病名満載、診断インフレ」と呼ぶ。
検査は診断のために行う。診断は薬を処方するために行う。医師は、適切な薬を出すことで、自らの責任を果たし、仕事をしたことになる。
それでも、手厳しいセラピストにかかると、「あなたたちは、治療に逃げてるんじゃないの? 私たちは、言葉ひとつでやってるのよ」と言って、これを「医者のアリバイづくり」とバッサリ切り捨てる。出した薬が効かなければ、それまでだ。
「一方的なご託宣と薬の処方だけでは患者が治療に参加できない。養生と手当てはどこへ行った? 薬を出すには、その性質と効能を十分に検討し、不可欠なもののみを必要最低限出すことが基本」というのが、直美先生をはじめとする多くの漢方医の姿勢である。
西洋医学の薬は、患者に与えるインパクトの大きいものが多い。抗がん剤などのように、Aの薬の功罪の罪の部分を和らげるためにBの薬を使い、同じ理由でCを使うといった併用は、患者に負担の大きい方法である。
これに対し、漢方薬は、「合剤(ごうざい)」といって、ひとつの薬の中に複数成分がよりあわされ、穏やかに効いて薄紙を剥ぐように少しずつ心身の恒常性を取り戻していくようにつくられている(もちろん漢方薬の中にも効き方の強いものもある)。
漢方薬の多彩な効き方を熟知した医師は、必然的に繰り出す玉が多くなり、相手に合わせた処方ができる。漢方薬は、西洋医学がとりこぼしがちな慢性疲労症候群やパニック障害、認知症などに効果を上げるほか、がん治療の副作用軽減のために併用されることが多い。
地域ネットワークと体内連続スイッチ
この日、以前から耳にしていた「オープンダイアローグ」の話も出た。こちらは、薬ではできない部分での連携であり、フィンランドで生まれたアプローチである。
病を抱えたひとりの人のまわりに、医師、看護師、ケアマネジャー、ヘルパー、薬剤師などあらゆる人がひとつの輪となって心を合わせて支援することは、在宅ケアでは不可欠なものとなっている。「ダイアローグ」は対話であり、かかわるすべての人の間に存在する対話によって、病を癒し、人生の最終段階にある人の心を安らかなものにしていく。
関わる人たちが情報を共有するために連絡ノートを活用する話などは、認知症のケアなどでも行われており、昨年の10月には、朝日新聞社主催の「看取り――幸せな人生の最終章とは」という講演会で、滋賀県東近江市に根を張って活動する花戸貴司医師と、看取りの風景を写真に残す國守康弘さんの話を聴いた。
「地域まるごとケア」という言葉と、「本人が元気になるなら、孫やひ孫も立派な関係者として輪の中に入ります」と語られたのが印象的だった。
同じようなことに横田先生も取り組まれている。医師ひとりだけでは手の回らないところに、別な専門職の力を借りる。そのために、自分で力のある人を探すことを日頃から心がけ、それが患者の助けになることで先生自身がさらにパワーアップしているようにお見受けした。
効いているのは、町医者ならではのネットワークである。内科、精神科、婦人科など、科を超えてゆるやかに地域で連携してきた阪神女医ネットでの経験が生かされている。医療だけでなく、整体もカウンセリングも、患者にいいことは、どんどん活用していく。
がんの疑いがあるといわれた患者は、ふつうは検査とその結果を聞くのに、病院に最低3回は行かなければならず、その間の恐怖と不安でメンタルがもたないことがある。しかし、地域に豊かなネットワークがあれば、診断で必要と思ったCTを連携機関に連絡して即刻検査し、1日で結果がわかる。大病院ではありえないことが在野の医師にはできる。
そのスピードのおかげで、患者はただちに覚悟せざるをえない。この時間短縮が、どれほど人の心を助けるかわからない。
「あなたはやがて死にます」と宣告されることは、たしかに残酷なことだ。
しかし、それを受け入れて、「今、私にできることは何?」と、考え方を変えた瞬間、患者に起きる変化がある。超多成分薬剤である漢方薬は、抗炎症作用や微小循環*の改善など、体内でドミノ倒しのようにどんどんスイッチを入れていく。
それは、体の中で薬ができていくことでもある。人の心がそれを促進する。
「日本の医師だけが西洋薬と漢方薬を同時に処方できます。統合医療的な考えをもちながら、上手に漢方薬を使って患者のQOLを上げていくことで、その人の人生に大きな変化を起こすことができる」と横田先生は語り、「町場が総合病院になる」と締めくくった。
*微小循環 人間の体内では、肺から取り入れた酸素が動脈を介して心臓へ送られ、心臓をポンプとして、血流に乗って全身に届けられ、二酸化炭素を回収して再び肺でガス交換している。血液は、太い血管から分岐して、組織内に細かい網目のように張り巡らされた毛細血管へと分配され、組織のすみずみでガス交換、栄養供給、老廃物回収が行われる。微小循環は、この毛細血管と組織との間の物質交換を担い、恒常性維持や免疫力の向上に大きな役割を果たす。