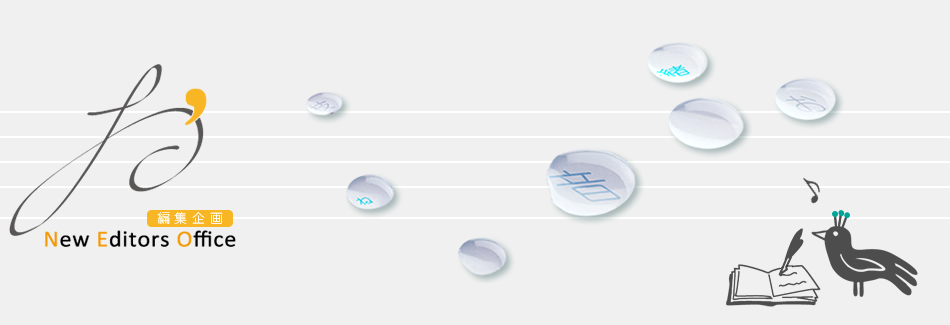ずっと昔、酸素窒素の業界で取材をしていた。見慣れない技術用語に圧倒されながら、せっせと過去の記事を読み、那野比古さんの半導体の本を持ち歩き、図書館でレーザについて調べた。工業ガスの技術用途は、鉄鋼、化学、半導体、食品、医療など幅広い。炭酸ガスやアセチレンと書いたところで、溶接のことも金属のこともまったくわからない。「ナフサ」という言葉は技術者との会話によく登場したが、それが何なのかも知らずにいた。
二十年以上のブランクを経て、最近また化学や機械などの技術用語に触れるようになった。ヤマ勘は相変わらずだが、わずかな手がかりでもあればありがたい。そんな動機で、国立科学博物館の産業技術史講座を受講した。タイトルは、「石油化学の技術体系と技術系統化」。講師は、通産省や三井化学を経て現在は日本化学会フェローの田島慶三氏である。
石油化学技術の隆盛期といえば、1970年代。意外にも、石油化学技術は、既存の教科書では体系化が十分とはいえず、田島氏は、各原料について、年代ごとに製法を書き記して再分類を試み、石油化学工業の定義そのものも見直した。
通説では、石油化学工業とは、「石油を基礎原料とする化学工業」と定義される。田島氏はこれを、「石油・天然ガスを原料として石油基礎製品・有機工業薬品・高分子を製造する化学工業」と新しく定義し直した。この日の話は、終始この3つの分類に沿って進められた。
石油化学製品は、通常ダイレクトに消費者に届くことはない。炭素数により無数の中間製品を経て、無機化学品や低分子または高分子の最終製品となる必要がある。四大汎用樹脂は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリスチレンであり、日本は多品種生産を特徴とする。
石油化学の時代は、1950年代終わり頃に始まり、高度経済成長期、1973年と1979年の二度のオイルショックを経て、1983年以降、レーガン大統領の頃、輸入自由化すなわち価格自由化の構造改善期に入る。1990年代に内需が飽和し、中国向け輸出が増加した頃は、高分子革命でプラスチック全盛となる。2008年、リーマンショックで内需はさらにしぼみ、過去3年でエチレンプラント3基が停止された。現在は、輸出比率35パーセント、輸入比率15パーセントだそうだ。
最近は、コンビナートの夜景ツアーが人気だが、1970年代は公害、1980年代は競争力を失った不況産業、1990年代は脱石油化学などといわれ、いまひとつ華々しいイメージに欠けるのが石油化学である。しかし、日常生活ではいたるところに高分子材料がある。1950年代の日本の高分子材料革命は、流通革命、つまりスーパーマーケットの登場によって起こった。それまでの量り売りから商品をパッケージするスタイルへの変更で、ポリエチレンやポリスチレンが大量に使われるようになった。カーボンファイバーを固めるエポキシ樹脂や、マトリックス樹脂などもある。
製法は原料ごとに異なり、できる製品もさまざまだ。アメリカのエチレンプラントの規模が100万トンといっても、原料の成分が日本とは異なるために、成分を分離するプラントの構造は、日本のほうがはるかに複雑になるという。また、石油化学独自の技術以外に、石油化学以前からあった油脂化学や石炭化学の技術を継承していたり、復活させたりしており、途絶したセルロース化学、発酵化学の技術も合流して、現在の高分子製造技術ができているというのは、いかにも化学っぽい現象であり、面白い。
新潮流として、基礎製品ではさまざまなプロピレン製造技術が開発され、有機工業薬品では、オレフィン化学(2000年代以降、メタセシス反応が登場)とパラフィン化学が主流、高分子製品では、配位アニオン結合を中核技術とし、開環メタセシス重合やポストメタロセン触媒などが盛んとのことだが、昔と同じく、このあたりはひとつひとつ調べないことにはちんぷんかんぷんである。21世紀に入ってからはバイオエタノールが普及し、アメリカでは、トウモロコシ畑の1/4がエタノールになっている。
一般に、石油化学技術は、アメリカを母、ドイツを父として生まれたといわれるらしいが、田島氏はこれも少しちがうと考えている。1890年から1900年にかけて、低温蒸留の技術が登場したことに大きい意味があったようだ。ここでは懐かしいドイツの産業ガスメーカー・リンデの名前が出てきて嬉しかった。ドイツリンデの子会社リンデエアプロダクツ(エアプロダクツは、アメリカのエアプロダクツ・アンド・ケミカルズを指す)は、アメリカのユニオン・カーバイド(UCCという略称をはじめて聞いたときはコーヒーの会社だと思ったものだ)とともに、天然ガスからエタンを分離して、1920年代のアメリカの高分子時代の幕開けに貢献している。酸素・窒素の技術は、やっぱり歴史のあるものなのだ、と、久しぶりに楽しく思い出した土曜の午後(2016.9.24)である。