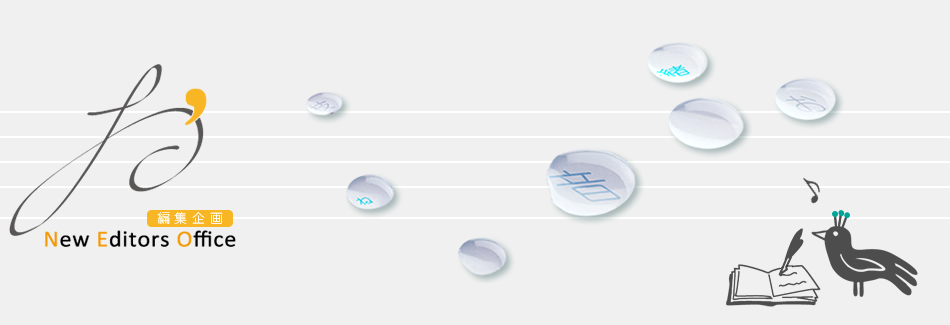2013年秋に日本で公開されたイタリア映画の「眠れる美女」(マルコ・ベロッキオ監督)を、先月観る機会があった。仕事で終末期医療についての文章を読んでいた矢先のことである。この作品は、2009年に実在したイタリアの尊厳死事件を扱っている。
21歳で事故に遭い、17年間昏睡状態のエルアーナ・エングラーロという女性をめぐり、延命治療の中止を求める家族と死を認めないカトリック教会、教会の影響下にあり延命措置続行の法案を通そうとする議会の三者の立場を軸に、2月7日から10日までのその周辺の人々の心と行動をフィクションで描く。
主に三組の人々が登場する。議会の法案に賛成の票を投じるよう迫られている政治家のベッファルディ、その娘でエルアーナの目覚めを祈るため教会のデモに参加するマリア。病院の医師パッリドと彼の前で手首を切り意識を失う薬物中毒の女ロッサ。さらに、植物状態にある娘ローザと看病のために女優業を引退した母。登場しないエルアーナを含め、事情の異なる三名の眠れる美女がいる。
ベッファルディは、延命続行への賛成投票に気が進まない。彼には、長く闘病生活にあった妻に懇願され、延命のための機器のスイッチを自分の手で止めた過去がある。息をしなくなった妻をかき抱き泣いても、後悔はなかったはずである。回復の見込みのないエルアーナの家族が延命停止を望んでいるのに、なぜその意思に反する決定を下す側に与せねばならないのか。パウロ二世も、「神の家へ帰そう」と言っているではないか。自ら反対の意思を表明して議員を辞す、とまで思いつめる。
娘のマリアは、教会へ向かう途中で偶然落ちた恋に気をそがれ、祈りのデモをエスケープしたりしている。恋の相手ロベルトの弟は精神不安定な青年である。彼には、エルアーナの奇跡的な目覚めを祈る人々が偽善者にみえる。デモに乱入し、警察へ連行される。
生きることに投げやりな女ロッサの腕には無数の針の跡がある。生きていてもしかたがない。死を妨げる医師パッリドの存在は、彼女には邪魔なばかりだ。
自宅でさまざまな管につながれ、かろうじて生きている二十歳そこそこの娘ローザを看病する母は、キャリアを捨て、聖女のように娘に尽くしながら、自分を偽善的だと感じている。声高くエルアーナの目覚めを祈るシーンと、手を洗わずにはいられないと口走る場面から強迫的な性格であることがうかがわれる。息子は母を自由にしたい。そのためにある行動をとるが、未遂に終わる。
この映画には、自らのあるいは家族の死を願う人が出てくる。第一にベッファルド議員の妻。第二が病院で手首を切った薬物中毒の女ロッサ。彼女は短い意識消失から目覚めても病院の窓から飛び降りようとして、医師にとりおさえられる。第三に動かぬ娘を自宅で看病し続ける母親を見て、彼女が女優にもどれるよう解放したいと思う息子だ。
結局、エルアーナと議員の妻の二人は死に、医師パッリドによって生へと引き戻された薬物中毒のロッサと、植物状態のローザの二人は死なない。「死なせるまい」とする人がいるのは同じなのに、ロッサには、孤独な彼女がパッリドとかわす会話にかすかな希望を感じ、物言わぬローザにはまた別のものを感じる。母親の祈りかエゴの力で生を続けさせられている娘には、自分の感情を表現する手段はない。ただ生きているだけの状態を彼女は望んでいるのだろうか。
生も死も自分で選べないと言うが、この映画で明確に選んでいるのは、ベッファルドの妻である。この場合、夫という他者の力を借りて生を終わらせた。ここにあるのは、延命治療を拒否する意思である。延命治療とは誰が何のためにするものか。状況は多様でひとことではいえないが、まず、人の生の「終末期」ということを考えなければならない。最近この概念は、「人生の最後の段階」と表されるようになったが、簡単に言えば、死がその身に迫り、回復のみこみのない状態ということである。重病の人や高齢の人に異変が起きた時は、これに相当する状況になることが多い。
延命処置をほどこされる場は、一般に病院である。どこかで倒れて意識を失うと、たいてい救急車で病院に運ばれ、「蘇生」措置を受ける。呼吸がうまくできなければ酸素を入れ、血圧が下がっていれば血流を増す措置をして、心臓の機能を助ける。血液中の微妙なミネラルバランスも維持する。極度の栄養不良では、栄養成分も体内に注入する。息を吹き返したら、今度はそれが「治療」として続けられる。その後の進展次第でいつの時点か、それは「延命」の措置に変わるようである。その境目や意識のない患者の状態によって、周囲の人の心に準備がなければ、医療者の判断に従うことしかできないのが自然の状態だろう。